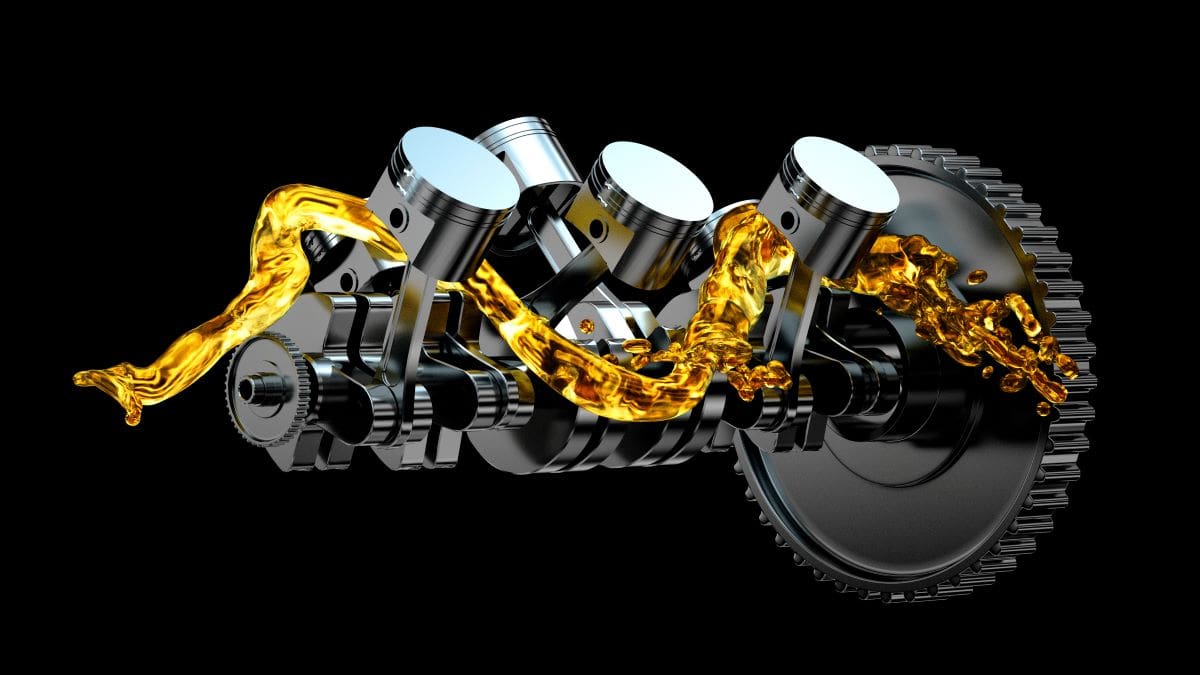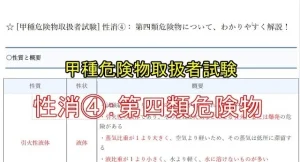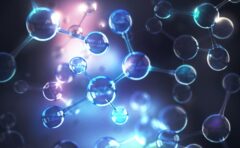こんにちは!
前回 (下の記事) に続き、今回も甲種危険物取扱者試験の「性消」について、解説していきます。
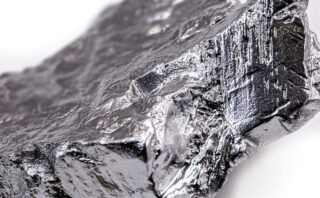
今回のテーマはこちら!
性質と概要
まずは、第四類危険物の性質と概要です。
第四類危険物は引火性液体で、主な性状と概要はこちらの表のとおりです。
| 性質 | 性状 | 概要 |
引火性液体 | 液体 |
|
火災予防と消火方法
以上の特徴から、第四類危険物の火災予防として、主に以下の点に注意が必要です。
- 炎、火花、高温体などとの接近、加熱を避け、みだりに蒸気を発生させないこと
- 十分な通風換気によって、燃焼範囲の下限値より低く保つこと
なお、燃焼範囲については、次のトピックで詳しく説明します。
そして、第四類の消火方法は、可燃物の除去や冷却が困難であることから、空気遮断による窒息消火が有効です。
消火剤としては、強化液、泡、ハロゲン化物、二酸化炭素、粉末などが使用されます。
また、消火に際しては、以下の注意事項もあります。
- 液比重が\(1\)より小さい危険物は、水に浮いて火災の範囲を広げるため、注水は不適当
- アルコールなどの水溶性液体の場合は、水に溶けて泡が消滅してしまうため、普通の泡剤ではなく耐アルコール泡 (水溶性液体用泡消火剤) を使用
第四類の主な危険物
第四類危険物には、特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類が該当します。
主な危険物は以下の表のとおりです。
また、燃焼範囲とは、燃焼が可能となる可燃性の蒸気と空気との混合気体の比率のことで、混合気体中の可燃性蒸気の容量を百分率で表します。
| 分類 | 品名 | 水溶性 | 引火点 | 発火点 | 沸点 | 燃焼範囲 (\(\%\)) |
| 特殊引火物 | ジエチルエーテル | △ | \(-45^\circ \rm{C}\) | \(160^\circ \rm{C}\) | \(35^\circ \rm{C}\) | \(1.9 \sim 36\) |
| 二硫化炭素 | × | \(-30^\circ \rm{C}\) | \(90^\circ \rm{C}\) | \(46^\circ \rm{C}\) | \(1\sim 50\) | |
| アセトアルデヒド | ○ | \(-39^\circ \rm{C}\) | \(175^\circ \rm{C}\) | \(20^\circ \rm{C}\) | \(4.0 \sim 60\) | |
| 第一石油類 | ガソリン | × | \(-40^\circ \rm{C}\)以下 | \(300^\circ \rm{C}\) | \(40^\circ \rm{C}\) | \(1.4 \sim 7.6\) |
| ベンゼン | × | \(-10^\circ \rm{C}\) | \(498^\circ \rm{C}\) | \(80^\circ \rm{C}\) | \(1.3 \sim 7.1\) | |
| トルエン | × | \(5^\circ \rm{C}\) | \(480^\circ \rm{C}\) | \(111^\circ \rm{C}\) | \(1.2 \sim 7.1\) | |
| メチルエチルケトン | ○ | \(-7^\circ \rm{C}\) | \(404^\circ \rm{C}\) | \(80^\circ \rm{C}\) | \(1.7 \sim 11.4\) | |
| アセトン | ○ | \(-20^\circ \rm{C}\) | \(465^\circ \rm{C}\) | \(57^\circ \rm{C}\) | \(2.15 \sim 13.0\) | |
| ピリジン | ○ | \(20^\circ \rm{C}\) | \(482^\circ \rm{C}\) | \(115.5^\circ \rm{C}\) | \(1.8 \sim 12.4\) | |
| アルコール類 | メタノール | ○ | \(11^\circ \rm{C}\) | \(385^\circ \rm{C}\) | \(65^\circ \rm{C}\) | \(6.0 \sim 36\) |
| エタノール | 〇 | \(13^\circ \rm{C}\) | \(363^\circ \rm{C}\) | \(78^\circ \rm{C}\) | \(3.3 \sim 19\) | |
| 第二石油類 | 灯油 | × | \(40^\circ \rm{C}\)以上 | \(220^\circ \rm{C}\) | \(145^\circ \rm{C}\) | \(1.1 \sim 6.0\) |
| 軽油 | × | \(45^\circ \rm{C}\)以上 | \(220^\circ \rm{C}\) | \(170^\circ \rm{C}\) | \(1.0 \sim 6.0\) | |
| クロロベンゼン | × | \(28^\circ \rm{C}\) | \(593^\circ \rm{C}\) | \(139^\circ \rm{C}\) | \(1.3 \sim 9.6\) | |
| 第三石油類 | 重油 | × | \(60-150^\circ \rm{C}\) | \(250^\circ \rm{C}\) | \(300^\circ \rm{C}\) | – |
| アニリン | △ | \(70^\circ \rm{C}\) | \(615^\circ \rm{C}\) | \(184.6^\circ \rm{C}\) | \(1.3 \sim 11\) | |
| グリセリン | 〇 | \(177^\circ \rm{C}\) | \(370^\circ \rm{C}\) | \(290^\circ \rm{C}\) | – | |
| 第四石油類 | ギヤー油 | × | \(170-310^\circ \rm{C}\) | – | – | – |
| シリンダー油 | × | \(250^\circ \rm{C}\) | – | – | – | |
| 動植物油類 | アマニ油 | × | – | – | – | – |
※ 〇:溶ける △:少し溶ける ×:溶けない
また、第四類危険物の分類条件は、下の表のとおりです。
| 分類 | 該当条件 | 指定数量 |
| 特殊引火物 | 1気圧において、発火点が\(100^\circ \rm{C}\)以下のもの、または引火点が\(-20^\circ \rm{C}\)以下で沸点が\(40^\circ \rm{C}\)以下 | 非水溶性、水溶性ともに \(50\ \rm{L}\) |
| 第一石油類 | 1気圧において、引火点が\(21^\circ \rm{C}\)未満 | 非水溶性のものが\(200\ \rm{L}\)、水溶性のものが\(400\ \rm{L}\) |
| アルコール類 | 炭素数3までの飽和1価のアルコール (変性アルコールも含む) | \(400\ \rm{L}\) |
| 第二石油類 | 1気圧において、引火点が\(21^\circ \rm{C}\)以上\(70^\circ \rm{C}\)未満 | 非水溶性のものが\(1000\ \rm{L}\)、水溶性のものが\(2000\ \rm{L}\) |
| 第三石油類 | 1気圧において、引火点が\(70^\circ \rm{C}\)以上\(200^\circ \rm{C}\)未満 | 非水溶性のものが\(2000\ \rm{L}\)、水溶性のものが\(4000\ \rm{L}\) |
| 第四石油類 | 1気圧において、引火点が\(200^\circ \rm{C}\)以上\(250^\circ \rm{C}\)未満 | \(6000\ \rm{L}\) |
| 動植物油類 | 動物の脂肉など、または植物の種子もしくは果肉から抽出したもので、1気圧において、引火点が\(250^\circ \rm{C}\)未満 | \(10000\ \rm{L}\) |
第一 ~第四石油類については、水溶性のものと非水溶性のもので指定数量が異なり、後者の方が指定数量が少ないです。
その理由は、消化の容易さに起因します。
水溶性のものと違い、非水溶性の場合は消火の際に水が使えず、その作業がより困難となるからです。
第四類に関しては、指定数量の倍数計算の問題がよく出題されるため、引火点による分類とそれぞれの指定数量をしっかりと覚えておきましょう!
各物質の性質、火災予防、消火方法
ここからは、各物質の説明に移ります。
特殊引火物
| ジエチルエーテル \(\rm{C_2H_5OC_2H_5}\) |
・性状および危険性
・消火方法 大量の泡、二酸化炭素、耐アルコール泡、粉末、ハロゲン化物の消火剤による窒息消化が有効 |
| 二硫化炭素 \(\rm{CS_2}\) |
・性状および危険性
・火災予防・貯蔵取扱いの注意
・消火方法 大量の水噴霧、泡、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物の消火剤による窒息消化が有効 |
| アセトアルデヒド \(\rm{CH_3CHO}\) |
・性状および危険性
・消火方法 耐アルコール泡、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物の消火剤による窒息消化が有効 |
| 酸化プロピレン \(\rm{CH_3CHOCH_2}\) |
・性状および危険性
・消火方法 耐アルコール泡、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物の消火剤による窒息消化が有効 |
第一石油類
| ガソリン |
・性状および危険性
・火災予防・貯蔵取扱いの注意 火気を近づけないこと ・消火方法 泡、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物による窒息消化が有効 |
| ベンゼン \(\rm{C_6H_6}\) |
・性状および危険性
・消火方法 泡、二酸化炭素、粉末の消火剤による窒息消化が有効 |
| トルエン \(\rm{C_6H_5CH_3}\) |
・性状および危険性
・消火方法 泡、二酸化炭素、粉末の消火剤による窒息消化が有効 |
| 酢酸エチル \(\rm{CH_3COOC_2H_5}\) |
| ・性状および危険性 水に少し溶け、液比重は\(0.9\) ・消火方法 耐アルコール泡、二酸化炭素、粉末の消火剤による窒息消化が有効 |
| ギ酸エチル \(\rm{HCOOC_2H_5}\) |
・性状および危険性
・消火方法 注水、二酸化炭素、粉末の消火剤による窒息消化が有効 |
| アセトン \(\rm{CH_3COCH_3}\) |
・性状および危険性
・消火方法 耐アルコール泡、二酸化炭素、粉末の消火剤による窒息消化が有効 |
| ピリジン \(\rm{C_5H_5N}\) |
・性状および危険性
・消火方法 耐アルコール泡、ハロゲン化物の消火剤による窒息消化が有効 |
アルコール類
炭素数が増加するとともに、蒸気比重、引火点、沸点は大きくなりますが、水に溶けにくくなります。
| メタノール \(\rm{CH_3OH}\) |
・性状および危険性
・消火方法 耐アルコール泡、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物による窒息消化が有効 |
| エタノール \(\rm{C_2H_5OH}\) |
・性状および危険性
・消火方法 耐アルコール泡、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物による窒息消化が有効 |
| イソプロピルアルコール \(\rm{(CH_3)_2CHOH}\) |
| ・性状および危険性 水によく溶ける ・消火方法 耐アルコール泡、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物による窒息消化が有効 |
| n-プロピルアルコール \(\rm{C_3H_7OH}\) |
| ・性状および危険性 水によく溶ける ・消火方法 イソプロピルアルコールと同様 |
第二石油類
| 灯油 |
・性状および危険性
・消火方法 泡、強化液、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物の消火剤による窒息消化が有効 |
| 軽油 |
・性状および危険性
・消火方法 泡、強化液、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物の消火剤による窒息消化が有効 |
| キシレン \(\rm{C_6H_4(CH_3)_2}\) |
・性状および危険性
・消火方法 泡、二酸化炭素、粉末の消火剤による窒息消化が有効 |
| クロロベンゼン \(\rm{C_6H_5Cl}\) |
・性状および危険性
・消火方法 泡、二酸化炭素、粉末の消火剤による窒息消化が有効 |
| n-ブチルアルコール \(\rm{C_4H_9OH}\) |
| ・性状および危険性 水に少し溶ける ・消火方法 灯油と同様 |
| 酢酸 \(\rm{CH_3COOH}\) |
・性状および危険性
・消火方法 耐アルコール泡、二酸化炭素、粉末の消火剤による窒息消化が有効 |
第三石油類
| 重油 |
・性状および危険性
・消火方法 泡、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物の消火剤による窒息消化が有効 |
| クレオソート油 |
・性状および危険性
・消火方法 泡、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物の消火剤による窒息消化が有効 |
| アニリン \(\rm{C_6H_5NH_2}\) |
・性状および危険性
・消火方法 泡、二酸化炭素、粉末の消火剤による窒息消化が有効 |
| グリセリン \(\rm{C_3H_5(OH)_3}\) |
・性状および危険性
・消火方法 二酸化炭素、粉末の消火剤による窒息消化が有効 |
第四石油類
| ギヤー油・シリンダー油 |
・性状および危険性
・消火方法 泡、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物の消火剤による窒息消化が有効 |
動植物性油類
| ナタネ油・アマニ油 |
・性状および危険性
・消火方法 泡、二酸化炭素、粉末、ハロゲン化物の消火剤による窒息消化が有効 |
まとめ
今回の記事は以上となります。
次回は第五類危険物について解説していくので、ぜひそちらもご覧ください!
間違いの指摘、リクエスト、質問などあれば、Twitter (https://twitter.com/bakeneko_chem)
かお問い合わせフォームよりコメントしてくださると、助かります。
それでは、どうもありがとうございました。